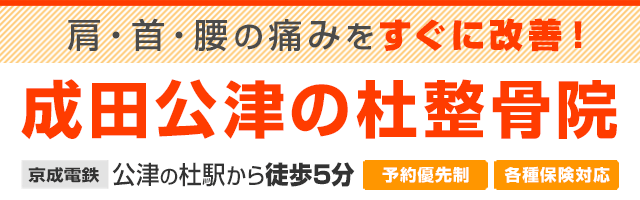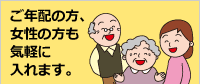巻き肩


こんなお悩みはありませんか?

最近、呼吸が浅くなったと感じることがある
首や肩、上半身の筋肉が硬くなり、常にこっているような感覚がある
スマートフォンを長時間見たあとに、姿勢が崩れていると感じることがある
デスクワークやスマートフォンの使用後に、頭が重くなるような頭痛に悩まされることがある
寝つきが悪くなったり、眠りが浅いと感じることがある
巻き肩について知っておくべきこと

巻き肩とは、肩が前方に内旋し、肩甲骨が前方に突出した状態を指す姿勢の乱れのひとつです。このような姿勢は、日常的に前傾姿勢を取ることが多い現代人に特に見られます。パソコン作業やスマートフォンの長時間使用が要因となり、無意識のうちに肩が前方へ巻き込まれる癖がついてしまうことがあります。
多くの場合、ご本人はその状態に気づいておらず、対策を取るタイミングが遅れてしまうことがあります。そのままの状態で長期間過ごすと、肩こりや首の痛み、さらには背中や腰への負担が大きくなり、日常生活においてさまざまな不調を引き起こす可能性があります。
巻き肩の原因は、肩関節の位置異常とそれに関連する筋肉のアンバランスにあります。このような筋肉の不均衡が続くことで、姿勢がさらに崩れやすくなり、不調が慢性化する恐れもあります。
症状の現れ方は?

巻き肩になると、胸まわりをはじめとする身体の前面の筋肉が縮こまり、呼吸が浅くなる可能性があります。呼吸が浅くなることで体内に取り込まれる酸素量が減少し、血流の悪化を招くおそれがあります。その結果、疲労感が抜けにくくなったり、頭痛や睡眠の質の低下など、さまざまな不調を引き起こすことがあります。
また、巻き肩の状態が続くと、首や肩の筋肉が緊張し、コリを感じやすくなります。筋肉の柔軟性が低下することで血流が滞り、肩甲骨の可動性が制限され、肩甲骨周辺に違和感や痛みを感じることもあります。さらに、猫背へと姿勢が崩れてしまったり、筋肉のハリが強まることで神経に影響を及ぼし、しびれなどの神経症状につながる可能性もあります。
その他の原因は?

巻き肩の原因として、スマートフォンやパソコンの操作が挙げられます。スマートフォンの画面に集中していると、無意識のうちに顔や首が前に突き出し、自然と肩が丸まりやすくなります。長時間のパソコン作業でも、同様に肩が前方へ出た姿勢を取り続けることになるため、巻き肩につながりやすいとされています。
また、睡眠時の姿勢も関係しています。横向きで寝る習慣がある方は、身体を丸めた姿勢になることが多く、肩が前方に出た状態で上半身の体重がかかり続けることで、巻き肩の一因となる可能性があります。
さらに、冬の寒さも影響します。寒さによって身体を縮めるような姿勢を長時間取りがちになり、背中が丸まって胸の筋肉が縮こまることで、肩が前に出た状態が習慣化してしまうおそれがあります。そのため、特に冬場は意識的に姿勢を正すことが大切です。
巻き肩を放置するとどうなる?

巻き肩の状態をそのままにしておくと、首や肩の痛みだけでなく、背中の筋肉にも負担がかかり、慢性的な背中の不調につながる可能性があります。また、首まわりの筋肉に過剰な負荷がかかることで、頭痛を引き起こす一因となることもあります。
さらに、肩や胸の前面の筋肉が短縮することにより、胸郭の広がりが妨げられて呼吸が浅くなる場合があります。呼吸が浅くなることで、体内に取り込まれる酸素の量が減少し、疲労感が取れにくくなったり、集中力の低下を感じやすくなったりすることがあります。こうした身体的な影響に加えて、精神的な不調を感じるケースもあるため、早めに対策をとることが大切です。
当院の施術方法について

巻き肩に対しては、骨格矯正、猫背矯正、肩甲骨はがしの施術メニューをご用意しております。
骨格矯正と猫背矯正は、姿勢のバランスを整えていく施術で、当院でも多くの方に受けていただいております。巻き肩だけでなく、背骨や骨盤の歪みにも対応できるため、全身の姿勢サポートにつながります。両者の違いとしては、猫背矯正はストレッチを中心に筋肉をやわらかくしながら姿勢の調整を目指すのに対し、骨格矯正は骨格のバランスに着目し、関節や骨格の動きを整えることで姿勢の軽減が期待できる施術です。
また、肩甲骨はがしは肩甲骨まわりに付着している筋肉を動かし、可動域を広げていく施術です。肩甲骨の動きがよくなることで、肩が開きやすくなり、巻き肩の軽減が期待できます。
軽減していく上でのポイント

まず、正しい座り姿勢を意識することが大切です。座るときは、天井から糸で吊るされているようなイメージを持つとよいでしょう。胸が自然に開き、顔が正面を向いている状態が理想的な姿勢となります。この姿勢を保つことで、巻き肩の悪化を防ぎやすくなります。
次に、スマートフォンの使い方にも注意が必要です。スマホを操作するときは、どうしても画面をのぞき込む前傾姿勢になりがちで、これが巻き肩の軽減を妨げる原因となります。肩への負担を減らすために、スマホは胸元ではなく顔の付近で持ち、視線を正面に保ちながら画面を見るよう心がけてください。
最後に、筋肉をしっかり伸ばし、正しい姿勢を維持することも重要です。巻き肩になると、胸の奥にあるインナーマッスルが硬くなり、肩甲骨が前に引っ張られやすくなります。巻き肩の軽減には、姿勢の調整とあわせて簡単なストレッチを行い、筋肉を柔らかく保つことが効果が期待できます。
監修

成田公津の杜整骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:岩手県盛岡市
趣味・特技:温泉巡り、映画鑑賞、人間観察